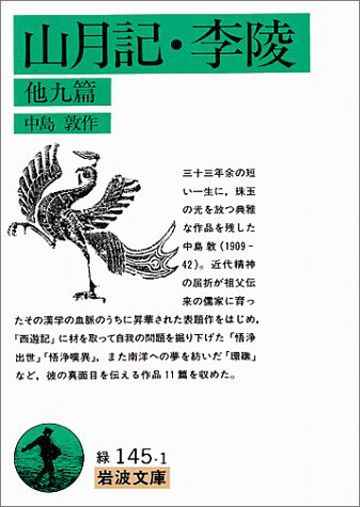
月曜日, 8月 13, 2018
中島敦の名人伝を楽しむ
1950年代後半に、国語として漢文読み下し文を必修科目があった高校時代を過ごしましたので、中島敦の小説は漢文を活性化し駆使したものとして魅力を感じていました。
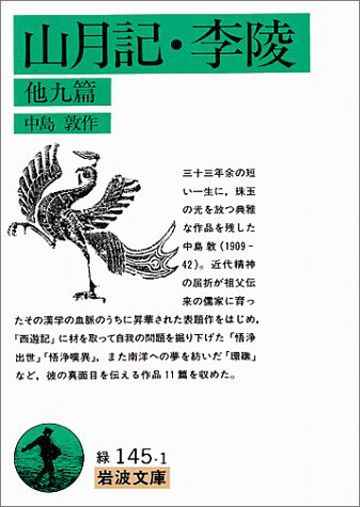
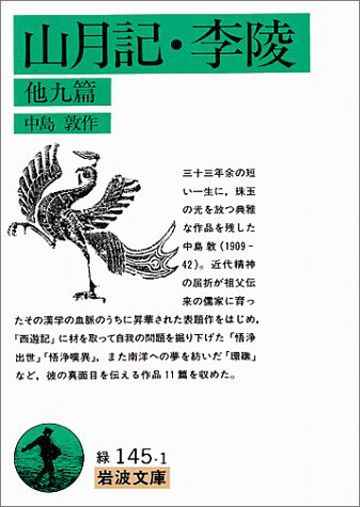
登録:
投稿 (Atom)
